�{���ɂ���
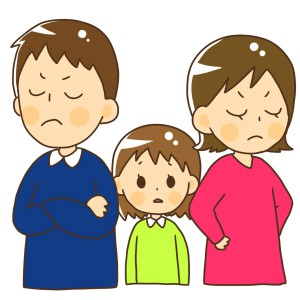
�q���̂��Ȃ��v�w�̗����̏ꍇ�́A�����҂����̖��Ȃ̂ł��݂����[������X���[�Y�ɗ����ł��A�ォ�睆�߂�Ƃ������Ƃ����܂葽������܂��A�����v�w�Ɏq���������ꍇ�����ȒP�ɂ͂����܂���B�����҂����̊�����ł͂Ȃ��A�q���̈ӎv�d���邱�Ƃ��K�v�ł����A�q��ĂɊւ�����K�ʁy�{���z�̂��Ƃ���������b������Ȃ���Ȃ�܂����B
�{����Ƃ́A�q������Ă邽�߂ɕK�v�Ȕ�p�̂��ƂŁA�q���̐�����⋳���ȂǁA�q��ĂɊւ����p�̑S�Ă��܂܂�܂��B
�{���Ɋ܂܂�����
�E�q���̐�����@�@�@�E�q���̌�ʔ�
�E�q���̋����@�@�@�E�q���̌�y��
�E�q���̈�Ô�@�@�@�E�q���̂��������@�Ȃ�
����͌o�ϗ͂ɉ����ė{���S����`��������܂��B���������ꍇ�́A�q���ƕʋ����Ă���e���������Ă���e�ɗ{�����x�������ƂɂȂ�܂��B���ۂɂ́A��e���e���������ē������邱�Ƃ����|�I�ɑ����̂ŁA���̏ꍇ�͕��e���x�������ƂɂȂ�܂��B
�q���̂��߂ɕK����낤
�q���ɂ͗{������錠��������܂��B�Ƃ��낪
�@�u���㑊��Ƃ�����肽���Ȃ�����A�{���͂��Ȃ炢�v
�@�u�q���ɉ�킹�Ă���Ȃ�����{���͎x����Ȃ��v
�@�u���Y��������ƕ��������ɗ{���͎x����Ȃ��v
�Ƃ����e�̏���Ȏ���ŗ{������Ȃ��P�[�X����������܂��B
�{���͎q���̐����Ɍ������Ȃ���Ȃ����ł��B���e�̏���ȓs���Ŏq���̌�����D���Ă��܂����Ƃ̂Ȃ��悤�A���O�ɂ�������b�������m���Ɏ��܂��傤�B
�{���̎Z�o���@
�{����͕���̔N��������x���ɂ���ĈقȂ�A���܂����z�Ƃ����̂͂���܂����B�����܂��b�������Ō��߂�̂������ł����A�ꉞ�ڈ��Ƃ��Ắu�������������̐e�Ɠ����������x���ŕ�点�邭�炢�̋��z�v�Ƃ���Ă��܂��B��̋L���́y�{���Ɋ܂܂������z����ڈ������ĂĂ݂�̂��ǂ��ł��傤�B
�܂��ƒ�ٔ������쐬�����y�{���Z��\�z���Q�l�Ɍ��߂�̂���̕��@�ł��B
���̕\�̌����́A
�@�q���P�l�̏ꍇ�i�O�`�P�S�܂Łj
�A�q���P�l�̏ꍇ�i�P�T�`�P�X�܂Łj
�B�q���Q�l�̏ꍇ�i�O�`�P�S�܂ł̎q�Q�l�j
�C�q���Q�l�̏ꍇ�i�O�`�P�S�܂ł̎q�P�l�A�P�T�`�P�X�܂ł̎q�P�l�j
�D�q���Q�l�̏ꍇ�i�P�T�`�P�X�܂ł̎q�Q�l�j
�E�q���R�l�̏ꍇ�i�O�`�P�S�܂ł̎q�R�l�j
�F�q���R�l�̏ꍇ�i�O�`�P�S�܂ł̎q�Q�l�A�P�T�`�P�X�܂ł̎q�P�l�j
�G�q���R�l�̏ꍇ�i�O�`�P�S�܂ł̎q�P�l�A�P�T�`�P�X�܂ł̎q�Q�l�j
�H�q���R�l�̏ꍇ�i�P�T�`�P�X�܂ł̎q�R�l�j
�ȏ���X����ɕ��ނ���Ă��܂��B
�������Ƃ��Ă�
�{�����x�������̔N���F�c���i��Ј��ƌl���Ǝ�ɕ��ށj
�{������鑤�̔N���F�����i��Ј��ƌl���Ǝ�ɕ��ށj
�ȏ���Q��ނ̎��������_��{���̖ڈ��Ƃ��Ă��܂��B
�{���Z�莖��
�E�{�����x�������F��Ј��@�N���S�O�O���~
�E�{������鑤�F�p�[�g�@�N���X�O���~
�E�q���P�l�@�Q��
�܂����̕\�̈�ԍ�����m�F���ĉ������B
�i�\�P�j�{���E�q�P�l�\�i�q�O�`�P�S�j
�ƋL�ڂ��Ă���܂��B
��̎��Ⴞ�Ǝq���͂P�l�łQ�ł��̂ł��̕\�����Ă͂܂�܂����A�q�����P�T�`�P�X���ƕʂ̕\���g�p���邱�ƂɂȂ�܂��B
���l�Ɏq�����Q�l�ȏ�̏ꍇ�����ꂼ��̏����ɍ������\��I��Ŏg�p���܂��B
�����{�����x�������̔N�������Ă����܂��傤�B
�x�������͍����̏c�����m�F���܂��B�悭���Ă݂�Ɛ��l���Q��ɂȂ��Ă邱�Ƃ�������܂��B����͊O���̐�������Ј��i���^�j�A�����̐������l���Ǝ�i���c�j�ɕ��ނ��Ă���̂ł��B���Ⴞ�Ɨ{�����x�������͉�Ј��ŔN�����S�O�O���~�ł��̂ŁA��ԍ����̎��̂S�O�O�ɓ��Ă͂܂�܂��B
�����{������鑤�̔N�������Ă����܂��傤�B
��鑤�͉��̉������m�F���܂��B��������c�����l�A���^�Ǝ��c�̂Q�s�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�������܂��B���Ⴞ���{������鑤�̓p�[�g�]�ƈ��łX�O���~�̔N���ł��̂ŁA��ԉ��̎��̂P�O�O�i���߂�����I���j�ɓ��Ă͂܂�܂��B
�����c���Ɖ�������������_�����Ă݂�ƁA�u�S�`�U���~�v�͈̔͂ɂ��邱�Ƃ�������܂��B
�܂莖��̏ꍇ���ƁA�ٔ���������{���̖ڈ����S�`�U���~�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
����������������܂Ŗڈ��ł��̂ŁA�K���������̒ʂ�Ɍ��肷��K�v�͂���܂���B���̎Z��\�͓����E���̍ٔ��������������̌��ʍ쐬���ꂽ���̂ł���A���ۂɎZ�肷��ۂ͒n���̎����g�ݓ���čl���邱�Ƃ��d�v�ł��B�܂���������͑��{���Ƃ̔N���i�����傫�����ƂƁA����ɕt���������Ɨ��̍������\���ɍl�����A���݂����[�����������ŗ{�������肵�܂��傤�B
�{�����x��������
�{����́A��{�I���q�������l�i�Q�O�j�ɒB����܂��Ƃ���̂���ʓI�ȍl�����ł��i�Q�O�Q�Q�N�S������̖��@�����ɂ���Đ��l�N��P�W�ɉ�����̂ŁA����ȍ~�͂P�W�܂Ŏx�����Α���邱�ƂɂȂ�\��������܂��j�B
�������A�K����������ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł͂���܂���B
�Ⴆ�Ύq������w�ɐi�w����ƂȂ����ꍇ�́A�u��w�𑲋Ƃ���܂��v�Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B���������̏ꍇ�u��w�𑲋Ƃ���܂Łv�Ƃ���ƁA�V��ł���ŗ��N�����ꍇ�͑��Ƃ��啝�ɒx��A�{���̎x�����`������������ɒ��������ƂɂȂ�̂ŁA�ʏ���w�𑲋Ƃ���N��́u�Q�Q�̒a�������߂����R���܂Łv�ƏI���m�ɂ������@������邱�Ƃ������ł��B
��������w���w���Ɋւ��Ă��ʏ�̗{���Ɋ܂܂��A�ʓr�������邱�Ƃ��\�ł��B���̏ꍇ�̕��S�����ɂ��Ă����O�ɘb�������Ă����܂��傤�B
������������茈�߂͌������łȂ��A�K���؋��Ƃ��Ďc���Ă������Ƃ��d�v�ł��B
�y�������c���z��y���������؏��z�Ƃ��������̂��쐬���邱�Ƃ��������E�߂��܂��B
���������v�w�̕Ј�����č������ꍇ�́H
�{�����x���������Ƃ鑤���A�č������Ƃ������R�����ł͗{���x�����`���A�܂��͎�錠���͎����܂����B
�������l�X�ȗ��R�ɂ��A�{�������z�E���z�����߂邱�Ƃ͉\�ł��B
�{���̑��z�E���z
�{���̎x�������ԂɁA�e�̌o�Ϗ�������ς�����ꍇ�́A�{���̋��z��ύX���邱�Ƃ��ł��܂��B
�{���̑��z�⌸�z�ɂ��ẮA��{�I�ɂ͕��ꂪ�b�������Č��߂邱�ƂɂȂ�܂��B�b�������ō��ӂł���������؏��ɂ܂Ƃ߁A���ӂł��Ȃ��ꍇ�͉ƒ�ٔ����ɗ{���̊z�̕ύX�����߂钲���\�����Ă܂��B����ł����ӂł��Ȃ��ꍇ�͍ٔ��������肵�܂��B
�ł͗{�������z�E���z���ł���̂͂ǂ�ȂƂ������Ă����܂��傤�B
| ���z | ���z |
|---|---|
|
|
�O�̋L���ŋL�ڂ����Ƃ���A�č������Ƃ������R�����ł͗{���S����`���������Ȃ�킯�ł͂���܂������A
�x���������č�����Ƃ̊ԂɎq�����ł����}�{�Ƒ����������ꍇ�́A�����ɉ����Č��z�����߂邱�Ƃ��ł��A
��鑤���č����āA�č�����Ǝq�����{�q���g�����A���̑���Ɍo�ϗ͂�����ꍇ�́A���z�܂��̓[���ƂȂ�\��������܂��B
�}���m���F�A��q�̑�����
�q�����̏������č������ꍇ�A���̘A��q�̑������͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���B
����́y�č����肪�S���Ȃ����Ƃ��Ă��A��q�ɑ������͂���܂����z
�܂��P�~�������ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�s�����Ɏv����������܂��A���͕s�����ł͂���܂���B
�Ȃ��Ȃ�y�A��q�͑O�v�Ƃ̐e���W����Ă��Ȃ��̂ŁA�O�v�Ƃ̑��������c���Ă����z����ł��B
�܂�č����肪�S���Ȃ��Ă��P�~�������ł��܂��A�O�v���S���Ȃ����Ƃ��ɑ��������������Ƃ������Ƃł��B
�����č����肪�A��q�ɂ���Y���Ă��������̂ł���A�⌾���ň②���邩�A�{�q���g�����邩�̂ǂ��炩�ɂȂ�܂��B
�������{�q���g�ɂ��đ厖�Ȓm�����m�F���܂��B
�{�q���g�ɂ́A�u���ʗ{�q�v�Ɓu���ʗ{�q�v�̂Q��ނ�����܂��B
- ���ʗ{�q�F�V�����e�i�{�e�j�ƌ��̐e�i���e�j�̗����̑������������ƂɂȂ�܂��B
- ���ʗ{�q�F�����Ƃ��Ďq�����U�Ζ����ł������g�ł��܂���B�܂����e�Ƃ̐e���W�͏I�����A�{�e�݂̂̑������������ƂɂȂ�܂��B
���ʗ{�q�͑O�̐e�Ƃ̐e���W�����S�ɒf���鉏�g�̂��߁A���ʗ{�q�������Ɍ������v�����ۂ���Ă��܂��B�{�q���g����������ۂ́A�q���ɂƂ��ĉ�����ԍK���Ȃ̂�����D��ɍl���܂��傤�B
�{���̎x������������

���c�����ŗ{���̎x�����̖����Ă��Ă��A�܂������x����������Ȃ��������A�������Ŏx���������Ƃ������Ƃ��悭������܂��B���̂悤�ȏꍇ�͂ǂ̂悤�Ȏ菇�ނׂ�����������Ă����܂��傤�B
�܂������̍ہA�������s�F���t�����؏����쐬���Ă������ǂ����Ō��ʂ͑傫���ς���Ă��܂��B�������s�F���t�����؏��Ƃ́A���ɓ�����O���t���Ă��܂����A�v�́w�{���̎x������ӂ����ꍇ�A�����ɋ������s�ɕ������x�Ƃ����ꕶ�����������������؏��̂��Ƃł��B���ꂪ����Ήƒ�ٔ������������s�̎葱���������Ă��炤���Ƃ��\�ɂȂ�܂��B
�������������؏����쐬���Ă��Ȃ������ꍇ��A�{���̎�茈�߂��s���Ă��Ȃ������ꍇ���A�ꉞ�����͉\�ł����A���̂悤�ȏꍇ�ٌ͕�m�Ȃǂ̐��Ƃɑ��k���邱�Ƃ��I�X�X�����܂��B
�����̎菇
�@����ƘA�������A�{�����x�����悤����
�ŏ��́A�d�b��[��������A���ډ�A�莆���o���Ȃǂ̉��ւȕ��@�ŁA����Ƃ̐ڐG��}��܂��傤�B
�������āA������Ɗ���������������Ŏx�����悤�����܂��B
�A���e�ؖ��X�ւ𑗂�
���e�ؖ��X���Ƃ́A�����̓����A���o�l�Ǝ��l�A�莆�̓��e�ɂ��āA�X�ǂ��ؖ������Ă����X�ւł��B
�@�I�Ȍ��͂͂���܂��A�؋��Ƃ��Ă̔\�͂������A���o�l�̖{�C�x��`���邱�ƂɂȂ�̂ŁA����S���I�v���b�V���[��^�������Ƃ��ł��܂��B
�B�������s���s��
��Ő��������������s�F���t�����؏�������ꍇ�A���̎��_�ʼnƒ�ٔ����ɋ������s�̎葱�������肢���邱�ƂɂȂ�܂��B
���������؏������ő�̖ړI�́A���̋������s���\�Ƃ��镶�������O�ɍ���Ă����Ƃ������ƂȂ̂ł��B
���̂��ߕ��͓��ɂ́A�������s�F��������K������Ă����܂��傤�B
�������s�ō������ł�����Y
- ����
- �a����
- �s���Y
- ������
- ���Y�i�M�����Ȃǁj
�{����̂悤�ɒ����ɂ킽���Čp���I�Ȏx���������߂�Ƃ��́A������������������̂���ʓI�ł��B
�܂��ʏ�̍����Ƌ����̂S���̂P�܂ł����������ł��܂��A�{���͋����̂Q���̂P�܂ō������\�ł��B����Ɉ�x�葱�����s���A�ߋ��Ɏx�����Ȃ������������łȂ��A�����ɂ킽���č��������F�߂��܂��B
���������̋����̍��������A���葤�̋Ζ����m���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ������ł���A������Ζ�������߂Ă��܂����ꍇ�͍������̌��ʂ������Ȃ��Ă��܂��Ƃ�����_������܂��̂ł����ӂ��������B
�܂����肪���c�Ǝ��������ꍇ�A�����Ƃ����T�O������܂���̂ŋ����̍������͕s�\�ł��B���������Ď��c�Ǝ҂ɑ��Ă���鍷�����ɂ́A�s���Y�E���Y�̍�������a�����̍��������l�����܂��B�s���Y�E���Y�̍������͎�Ԃ���p��������܂��̂ŁA���c�Ǝ҂ɑ��Ă͗a���̍��������ł����p����Ă����悤�ł��B
